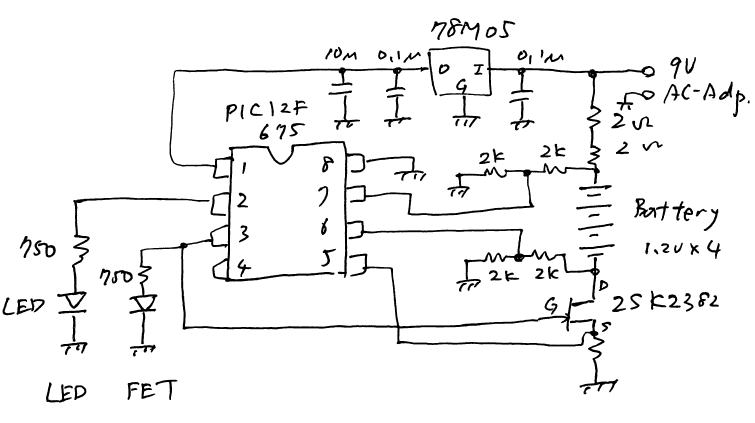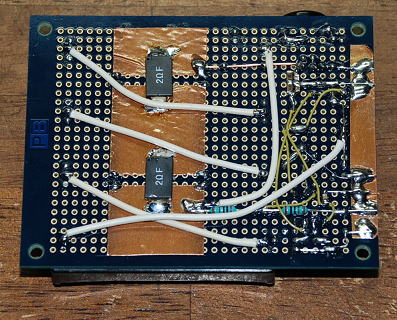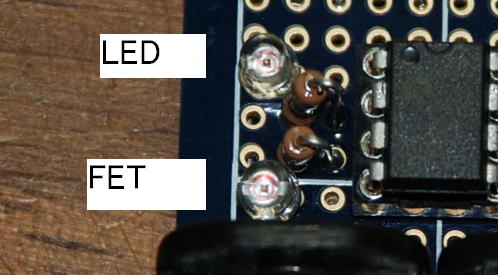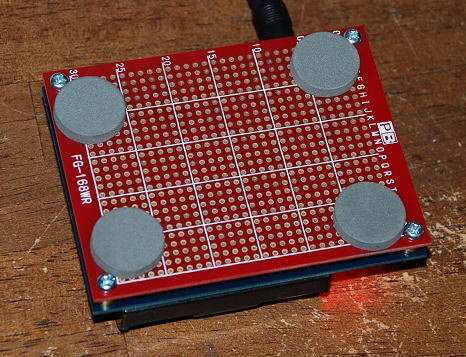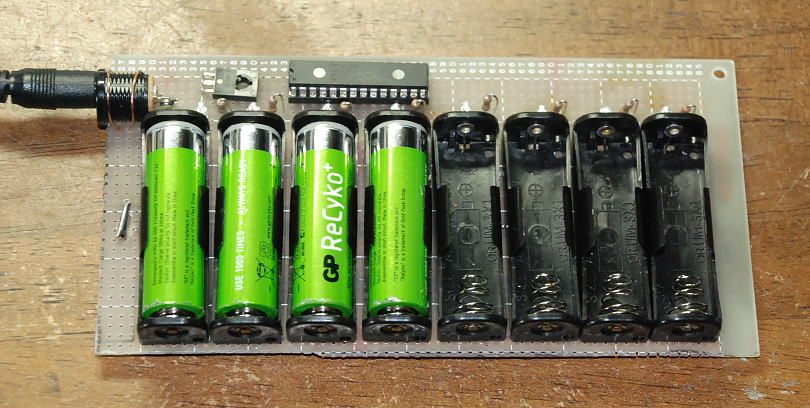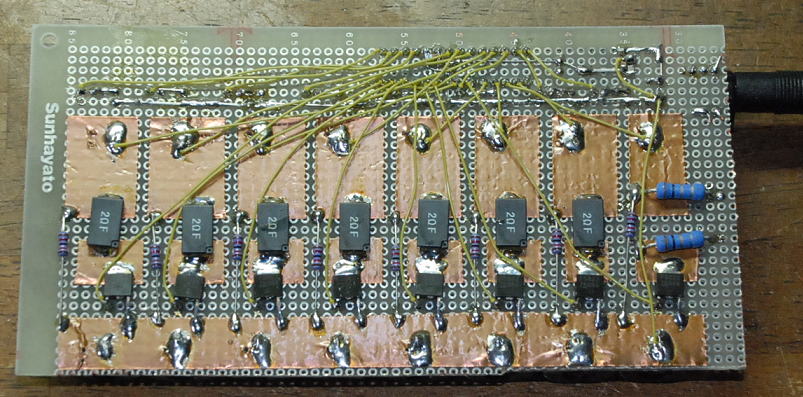�[�d���V������I�@2011.5.7
�c�c�r���U��������ēd�r�œ����悤�ɂ����̂͂����̂����A�d�r�̏[�d�킪���܂������q���ǂ��Ȃ��B
���g���Ă���[�d��͂P�O�N�O�ɍ�������̂ŁA�\���͂������ĊȒP�B
�[�d�r�ɒ�d�����Q���ԂS�U������������Ƃ������́B�d�r�̗e�ʂɂ��킹�ēd���l��I�Ԃ悤�ɂ��Ă����̂�
�d�r�ɂ�炸�[�d�\�Ȃ̂������ł��B��d����H�͕��ʂ̉�H�ł����A�����Ԃ̃^�C�}�[����������ɂ�
�����d��i���܂�Panasonic�j�̂`�m6780�Ƃ������̂������܂����B���Ԃ�H���Ŕ����Ďv���o�����悤��
�������̂��Ǝv���܂��B
�@�ʼn������q�����܂������Ƃ����ƁA�P�O�N�o�������������Ă���̂����ǁA�Ƃ��ǂ��[�d���o���Ă��Ȃ����Ƃ�����܂��B
�Ƃ����̂��\�P�b�g�̐ڐG�i�ړ_���_���H�j�s�ǂȂ̂��A�d��������Ȃ��Ƃ�������܂��B
���̏[�d��ł͓d��������Ă��邩�ǂ����̃`�F�b�N�͏o���Ȃ��̂ŁA���������e�X�^�[�Ń`�F�b�N���邱�Ƃ�
�K�v�Ȃ̂ł����A����͂��܂�ɂ��s�ւł��B
�Ƃ������ƂŁADDS�p�ɏ[�d�r�������Ƃ��������̂ŁA������@��ɏ[�d���V�����邱�Ƃɂ��܂����B

�P�O�N�O�ɍ�����[�d��B
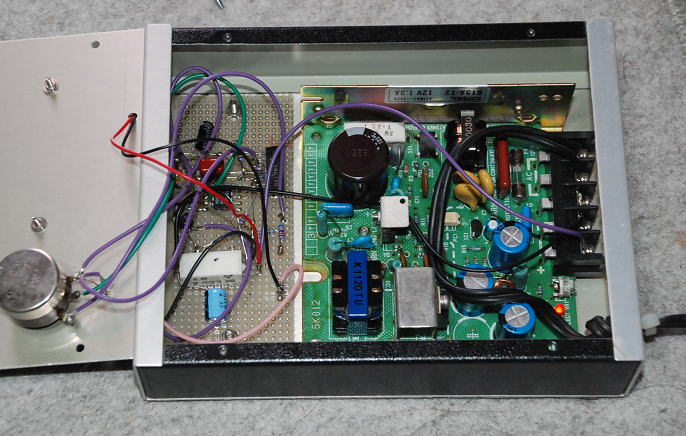
�����͂��Ȃ藐�\�i�j�B�X�C�b�`���O�d���ɒ�d����H�{�^�C�}�[��g�ݍ��݂܂������قƂ�ǂ��d���ł��B
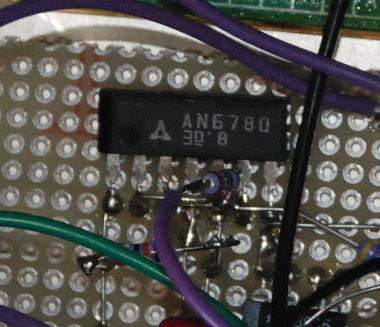 �@
�@
�^�C�}�[�Ɏg�����f�q�B���ꂪ���̏[�d��̗v�ł��B
�[�d���V������I
�[�d���V������Ƃ����Ă��A�s�̂ň��������Ă��邱�Ƃ����肠�܂�R�X�g��������̂��̂��炵���ł��B
�Ƃ������ƂŁA���i���ɂ�����̂����ō���悤�ɁA���}�̂悤�ȉ�H�ɂ��܂����B
��{�͓K���ɓd���𗬂��āA�K���Ȏ��ԂŎ~�߂�Ƃ������̂ł��i�j�B
�^�C�}�[�ɂ�PIC�������Đ��䂵�āA�ꉞ�f���^�s�[�N���o���ł���悤�ɂ��Ă݂܂����B
�ł���d����H�ł͂Ȃ��̂ŁA�f���^�s�[�N�����삷�邩�́H�H�H�ł��B
�܂��A�[�d��~�̏����͈��̎��Ԃ��o�����ꍇ�A���邢�̓f���^�s�[�N�i-�Q0mV)�����m�����ꍇ��
�v���O������g�߂A���v�ł��傤�B
�@���������^��8P��PIC�ł��A�i���O���͒[�q���R������͕̂֗��ł��B���̒[�q���������ƂŁA
�[�d�r�ɓd��������Ă��邩�ǂ����̊Ď����ł��܂��B
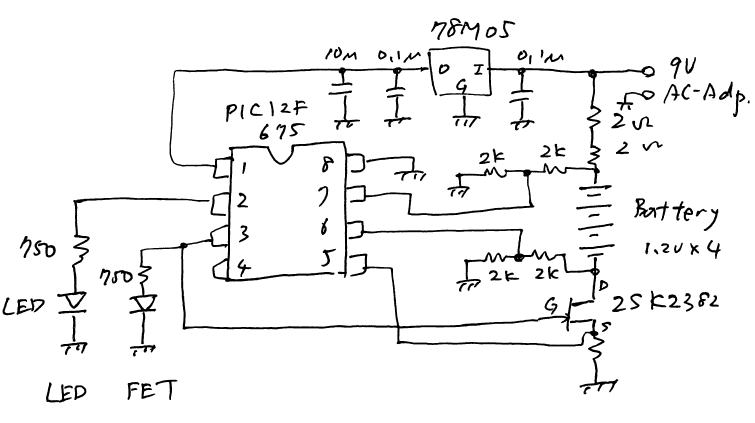
����A�V�������[�d��̉�H�}�BFET�̃\�[�X�ɂȂ����Ă����R�͂O�D�Q�Q��
���āA���̂��炢�̉�H�Ȃ̂ł����ɑg�߂����ł��B
�g�p�������i�͂���Ȋ����B
�@�v�����g��@ �F�@�@�@���܂��Ŗ�������̂��g�p�B
�@PIC12F675�@�@�F�@�@�@�Ƃ肠���������Ă��������́B���P�Q�O�~���炢�H
�@78M05�@�@�@�@�@�F�@�@�@�����ԑO��genpin.com�Ŕ������B�����������߂��P�O�O�ȏ㔃�����o��������B
�@2SK23852 �@�@�F�@�@�@�H���łS�Q�O�O�~�Ŕ����Ă��B�A���v�p�ɔ��������ǁA�����������Ȃ̂Ŏg���Ă݂��B
�@�o�b�e���@�@�@�@�F�@�@�@�H���̃j�b�P�����f�B�S�łV�X�O�~�B
�@�o�b�e���[�P�[�X�F�@������H���B
�@�k�d�c�@�@�@�@�@�@�F�@�@�@�ȑO�ɂT�O�O��������LED�����A�����ԍɂ������Ă����B�܂�����˂E�E�E�E
�@�R���f���T�@�@�F�@�@�@���܂�̃`�b�v���i���g���܂����B
�@��R�@�@�@�@�@�@�@�F�@�@�@�l�o�b�V�S�@�f�W�b�g�łP�O�~�������B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�d�����o�p�Q����R�i�H���łS�P�O�O�~���������ȁH�j

�d�r�̂��鑤�̎����̗l�q�B
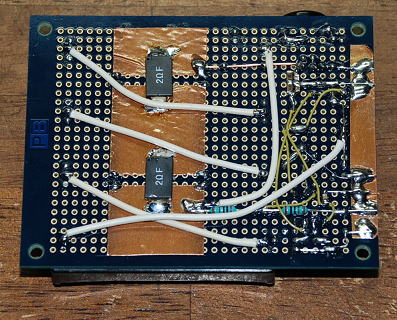
���c�ʂ̗l�q�B��R�̔M�������߂ɑ傫�߂̓����e�[�v��\��t�����B
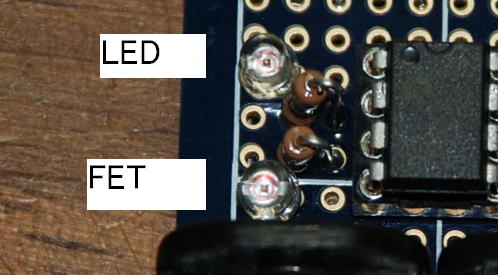
����m�F�p��LED���Q�Ƃ���܂����B
�����I
���̂��炢�̃n�[�h�Ȃ�R�O�����x�őg�߂܂����B�ŁA�����\�t�g��g�ݍ���ŏ[�d���Ă݂܂����B

�[�d���̗l�q�B
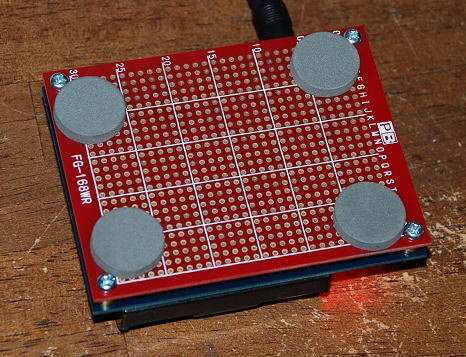
���ʂ͔z���ɐG����Ȃ��悤�ɁA�ʂ̊�ŊW�����Ă����܂����B
���i�S���H�j�͂P�O�O�~�ψ�Ŕ��������̂ł��B
���샂�[�h�́H
����͊��S�ɔ��Y�^�ł����A���̂悤�Ȋ����ł����Ă��܂��B
| ������ |
LED |
FET |
���� |
| �[�d�r�̎����҂� |
���� |
�P�b�Ԋu�ŒZ���_�� |
�d�r�����������܂Ŋm�F��Ƃ��Â�B
�d�r�����������͓̂d��������邩�ǂ��������m���Ă���B |
| ���O�[�d |
�_�� |
�_�� |
�[�d�r�������ɏ[�d����ꍇ�͓d�����s����Ȃ��Ƃ������̂ŁA
�Ƃ肠������T���Ԃ͖�����ɏ[�d����B |
| �{�i�[�d |
�Q�g���œ_�� |
�_�� |
�{�i�[�d�B�[�d���I����������͉��L�̂ǂ��炩�B
�@��莞�Ԃ��߂����ꍇ�i��Q�D�T���F�[�d�d���͖�760mA)
�@�f���^�s�[�N�����o�i�|�Q�O�����j
�Ȃ��A�[�d���ɓd�r�����O���ꂽ�ꍇ�́u�[�d�r�̎����҂��v
��ԂɂȂ�悤�ɐݒ�B |
| �[�d���� |
���� |
���� |
�[�d�����ł��B
���̏�Ԃœd�r�����O���ꂽ�ꍇ�́u�[�d�r�̎����҂��v
��ԂɂȂ�悤�ɐݒ�B�����ɐV�����[�d�r������鏀���ɂȂ�܂��B |
�Q�l���\�[�X���o�C�i���[�����J�B
�����Ȃ��Ă��m��܂���i�j�B
<�>���łɕ��d�������I�@2011.5.8
�[�d�r���c�ʂ��o���o���̂܂܁A�ď[�d����Ǝ�����Z������i�ߏ[�d�ɂȂ���̂��łĂ���j���Ƃ�����A
���łɕ��d�������܂����B��H�͂������ĊȒP�ŕ��ׂ͂Q���̒�R�Ƃ��āAFET�X�C�b�`��ON/OFF
���܂��B������PIC�œd�����Ď����ĂP�u�ȉ��ɉ�����������d����߂�Ƃ������̂ł��B
�@�S�̂łW�{�̓d�r��ON�^�n�e�e�ƁA�d���̊Ď��A�����ĕ��d�����̕\�������킹�ĂQ�S�{��IO������̂ŁA
�K���ɑ��̑���PIC16F886(28p)�������܂������A����Ă���Œ��i���͉�H�}���`�����ɍ�Ƃ��Ă��j��
���̐������肬��Ȃ̂ɋC�t���܂����i�j�B
�@�Ƃ����̂�PIC16F886�͂Q8P�ł����A���̂����R�{���d���B������I/O�̂P�{�͓��͐�p�iAD���͂ł��Ȃ��j�̂�
�����g����̂͂Q�S�{�����B�Ƃ������Ƃł��肬��ł����B
�@ �X�C�b�`�͂e�d�s�ɒZ�����m����M���m�Ȃǂ�����IC�ł����A�قƂ��FET�Ɠ����悤�ɂ�������̂�
�H���łP�O�Q�O�O�~�ł����B�X���Ŕ����܂������A�ʔ̂ɂ͂Ȃ��悤�ł��B
�֗��Ȃ̂ł܂��s�����Ƃ��ɂł���������ł����܂��傤�B
FET���X�C�b�`�Ƃ��Ďg�����Ƃ��̃����b�g�́A�i�n�m��R�����������̂ł���j�d���~�������������M���������A
�Q�[�g�d��������Ȃ��̂ŋ쓮�p�̒�R���Ȃ���i���܂萄���ł��Ȃ���������܂��E�E�E�E�B������
�o�C�|�[���͓d�������p�ɕK�v�ł��j�Ƃ����Ƃ���ł��B
�@�f�����b�g�͏��X���������Ƃł��傤���B�A
���̕��d��͑O�X����~�����������̂ł����APIC���g����悤�ɂȂ��Ă悤�₭���C�y�ɍ�邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂����B
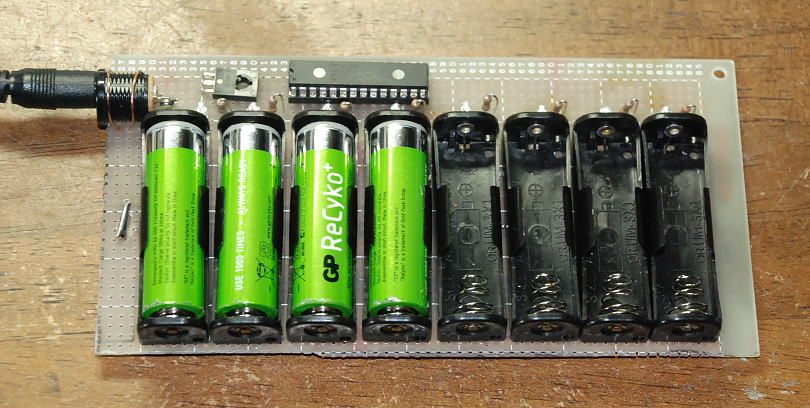
�P�O�[�d�r�̕��d��B���ꂼ��ʂɕ��d�Ǘ����ł��܂��B������P��PIC�ŏ����ł���̂ŕ֗��ł��B
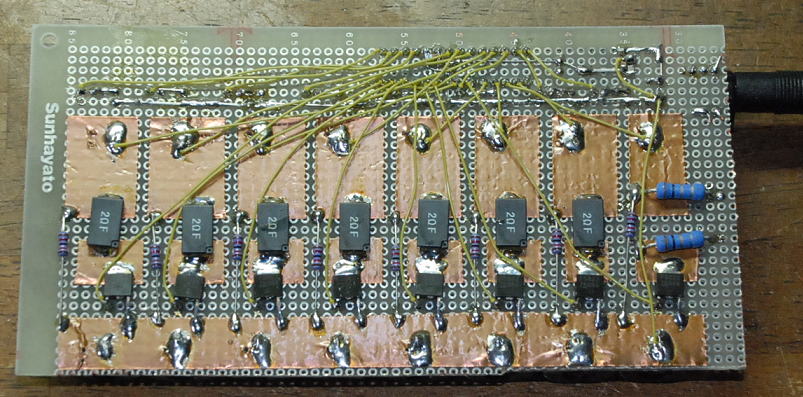
�����̗l�q�B����ɂQ���̒�R�ׂɂ��ăX�C�b�`�i�e�T�O�Q�Q�|�k�|�e�Q�Q�V�j��ON/OFF���Ă��邾���ł��B
14�N�Ԃ�̔��Y�^�@2025.3.28
PIC16F886�̃v���O����
| LED |
�o�b�e���[�d�� |
���l |
| �_�� |
1.2V�ȏ� |
|
| �������_�� |
1.1�`1.2V |
|
| �����_�� |
1.0�`1.1V |
|
| ���� |
1V�ȉ� |
��x1V�ȉ��ɂȂ�ƁA���d�����D
�ĕ��d����ꍇ�́A�d�r�����������B |
PIC�̃s���z�u��
�o�b�e���[�͉E���獶�ւP�`�W�ԁD
�����Ă���PIC16F886��AD���̓s���͂��Ȃ�ϑ��I�ł��D
�v���O����������������Ƃ��āAPIC18F27Q43���g���ꍇ��AD���͂����L�D
|
16F886 |
�ڑ��� |
PIC�̃s���z�u |
�ڑ��� |
16F886 |
|
|
|
|
1 |
E0 |
B7 |
28 |
LED8 |
|
|
| sAN0 |
sAN0 |
BATTERY8 |
2 |
A0 |
B6 |
27 |
LED7 |
|
|
| sAN1 |
sAN1 |
BATTERY7 |
3 |
A1 |
B5 |
26 |
LED6 |
|
|
| sAN2 |
sAN2 |
BATTERY6 |
4 |
A2 |
B4 |
25 |
LED5 |
|
|
| sAN3 |
sAN3 |
BATTERY5 |
5 |
A3 |
B3 |
24 |
BATTERY1 |
sAN9 |
��AN11 |
|
|
GATE8 |
6 |
A4 |
B2 |
23 |
BATTERY2 |
sAN8 |
sAN10 |
| sAN5 |
sAN4 |
BATTERY3 |
7 |
A5 |
B1 |
22 |
BATTERY4 |
sAN10 |
sAN9 |
|
|
|
8 |
GND |
B0 |
21 |
GATE1 |
|
|
|
|
GATE7 |
9 |
A7 |
Vcc |
20 |
|
|
|
|
|
GATE6 |
10 |
A6 |
GND |
19 |
|
|
|
|
|
GATE5 |
11 |
C0 |
C7 |
18 |
LED4 |
|
|
|
|
GATE4 |
12 |
C1 |
C6 |
17 |
LED3 |
|
|
|
|
GATE3 |
13 |
C2 |
C5 |
16 |
LED2 |
|
|
|
|
GATE2 |
14 |
C3 |
C4 |
15 |
LED1 |
|
|
(�����܂��H�j

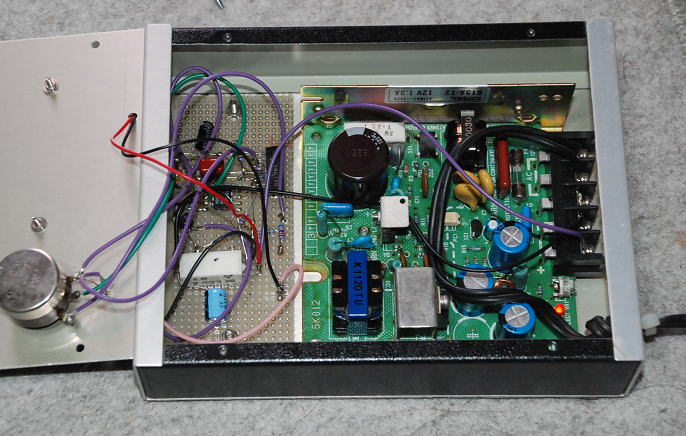
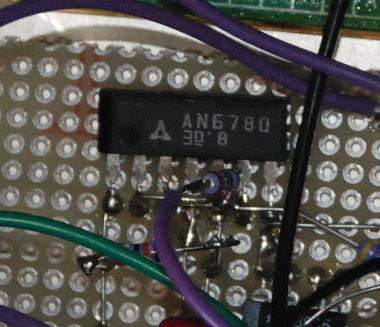 �@
�@